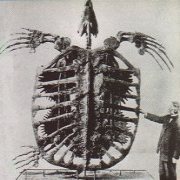| 話は少しそれるが、ここで”空飛ぶ円盤騒ぎ”について少々触れてみたい。僕らがイメージする円盤はTVや映画でのイメージの影響もあるが、おおむね統一されている。それは現代科学では造れないが、数十年後には我々でもなんとか実現しそうな雰囲気ではないだろうか。そしてそれは紛れもなく多くの人々の目撃情報に基づくものである。では、昔っから”この形”かというと、実はそうではない。18世紀以前には、なんとそれは・・帆船の形だったんだ!。 空飛ぶ帆船の目撃は、古くは9世紀にまでさかのぼる。リヨンの大司教アゴバールは、4人の囚人を護送してきた群集に出会った。彼らの話によると、4人が空飛ぶ船から地上に降りてきたところを捕まえたのだという。もちろん大司教は信じなかったが・・。また西暦956年には、アイルランドのクロエラの教会の屋根に、空飛ぶ船の錨(!)が引っ掛かったときの模様が伝えられている。比較的新しいものでは、1743年、英国のウェールズ地方の北西にあるアングルス島の農夫による、雲間を漂う帆船の目撃報告がある。彼の話によると、帆船の排水量は約90t、蜃気楼などではない証拠に船底の中央の竜骨がはっきりと見えたという。この千数百年に及ぶ、”空の不思議”すなわち”空飛ぶ帆船”という時代は、やがて終わりをつげる。続く19世紀に欧州の上空に出現したのは、”飛行船”であった。
飛行船目撃事件の最も有名なものは、1896年から翌年にかけて全米を大混乱に陥れたウェーブ(集中目撃)である。報告の大部分は中西部とテキサス州であったが、最盛期にはアイオワ、ミシガン、ワシントンの各州の上空で、葉巻型の有翼の飛行物体が、なんと数千人の規模で目撃されたのだ。当時、操縦可能な飛行船は、米国はおろか、最も技術の進んだ欧州諸国ですら、まだ飛んでいない。F・ツェッペリン博士の硬式飛行船の初飛行は、1900年7月2日のことである。米国の飛行船事件は1年足らずで下火になったものの、その後カナダ、スウェーデン、ノルウェー、ロシアなどで、次々と謎の飛行船の目撃が報告されはじめた。さらにこの謎の飛行船騒動は、1909年の英国に上陸する。その目撃報告は、わずか数ヶ月の間に英国全土に及び、政府はあまりの事態に飛行船撃墜用の高射砲を製作するまでに至っている。当時イギリスの敵国であり、最先端の航空技術を誇っていたドイツの偵察機では?という可能性も完全には否定できない。しかし1909年のドイツの飛行可能な飛行船はわずか3機で、当然英仏海峡を渡るような長距離飛行も、いくつかの報告にみられるような高速飛行の性能も、持ってはいなかった。
1937年5月6日の、飛行船「ヒンデルブルグ号」炎上事故を分岐点に、空の主役は飛行船から飛行機の時代へと突入する。これ以降の空の不思議は、皆さんもご存じのとおり、そう、”UFO”の登場だ。1947年6月24日
アメリカの実業家ケネス・アーノルド氏が、ワシントン州レーニア山付近で、9つの空飛ぶ円盤を目撃したのを皮切りに、以後、空飛ぶ円盤の目撃が、全世界で続発することになるのである。
|